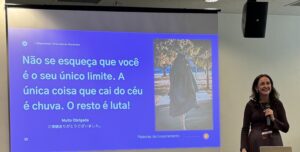在日ブラジル商工会議所は、会員の皆様あてに毎月ニュースレターをお届けしております。1月号では、大学講師のエリカ·ガルシア·ムラモト氏に群馬県内の大学における外国人留学生の実態調査についてご寄稿いただきました。
次世代のエンパワーメント:
群馬県内の大学における在住外国籍学生の実態
村本 エリカ・マリア
文化的、言語的多様性とグローバリゼーションは、世界規模で教育事情を一変させているが、日本も例外ではない。日本では、経済を活性化させるために外国人労働力が必要になったことから、1990年に改正された出入国管理及び難民認定法が施行され、三世までの日系人とその配偶者や子どもの日本国内での就労が認められた。
そのため、多くの家族が日本に定住することになったが、こうした労働者の子や孫には、出生地が日本でも日本国籍は与えられない。日本では国籍を付与するにあたって血統主義が採用されているためだ。しかし希望者は法的要件を満たせば帰化申請することができる。
彼らの教育の選択に目を向けると、日本の教育機関に子どもの教育を托したいと考える外国人家庭が多いことがわかる。日本の小中学校に在籍する日系人の子や孫は文部科学省の調査において「外国人児童生徒」と分類されているが、高等学校や特に大学・専門学校に通う在住外国籍生徒・学生に関する情報は不足しており、彼らの学業達成度の把握は困難な状況といえる。
中には、在日ブラジル人学校のような外国人学校を選ぶ家庭もある。在日ブラジル人学校は私立の学校で、ブラジル教育文化省(MEC)から在外ブラジル人のための教育機関として認可されている。日本では「各種学校」に分類されており、日本の学校と同等の教育機関としては扱われていないが、文部科学省はこうした学校の教育環境や経営状態の改善に対して支援している。外国人学校の多くは、生徒が本国に帰国した場合に学業を続けられるように、母国の教育制度に沿ったカリキュラムを採用していることが特徴である。ブラジル人学校、インターナショナルスクール、朝鮮・韓国学校、フランス人学校、ドイツ人学校などを含む127の外国人学校が各種学校として認可されている(2011年5月現在)。
現在、留学ビザを取得し日本の大学で学ぶ外国人留学生に関しては、出入国在留管理庁や法務省が詳細なデータを収集しているが、日本で育ち、暮らす在住外国籍学生の大学在籍状況は把握していない。我々が探すことができた過去の調査記録は、静岡県内でのアンケート調査のみであった。
筆者と3名の研究者[2]は、1990年代以降に外国人労働者の数が著しく増加した群馬県で、大学で学ぶ在住外国籍学生の実態調査を行った。県内の外国人住民数は総人口の3.8%に相当する72,315人で、出身国・地域は115に上る。ブラジル人住民の数は13,063人で国籍別では2番目に多い(2023年12月現在)。
本調査は群馬県内の14の大学を対象とし、内12大学から回答を得た。2022年度の大学在籍者数19,053人のうち、在住外国籍学生は11カ国・地域出身の94人で、内訳は中国が29人でトップを占め、以下ブラジル21人、ペルー15人、フィリピン14人、韓国6人、ボリビア4人、パキスタン4人、ベトナム3人、台湾2人、タイ2人、バングラデシュ1人と続いた。
彼らの出身校は、公立高校出身者が45人、私立高校出身者が14人、外国人学校出身者が5人、その他の学校出身者が8人であり、生徒の出身校に関するデータを非公表とした大学が2校あった。出身高校は多様であるが、大学進学を果たした学生の多くは、日本の教育システムを選択し、大学進学を果たしたと言える。
専攻は社会科学が40人と最も多く、次いで人文科学が24人であった。保健学と自然科学は各10人であった。工学系分野、その他の割合は低く少数であった。
新型コロナウィルス感染症のパンデミックが収束し、外国人労働者の増加、またそれに伴い、日本で学ぶ外国人児童生徒数も、今後増えることが見込まれている。そのため、日本で暮らす外国人の就職、就業に関する課題や、学業を修了していないといった学歴の課題がもたらす就業機会の格差などを考慮すると、日本で育つ外国籍児童生徒の就学、進学状況を初等教育から高等教育の全ての教育課程で把握し、確実に支援を行うことが不可欠である。
最後に、本研究から2点言及したい。第一に、日本で暮らす外国人家庭の教育への投資は増加しており、多様な背景を持ち、また学ぶ意欲のある多国籍の学生の受け入れが日本の大学で進んでいる点である。これは包括的かつ公正な社会の実現に不可欠な一歩である。第二に、本研究で示されたような客観的なデータは、幼少期に来日した、あるいは日本生まれだが日本国籍ではない人たちが、いずれ日本または海外で就業するまでの道のりを理解する上で、重要な意味を持つという点である。
本研究の結果から得られる成果は慎ましいものである。しかしながら、外国籍コミュニティーや教育関係者、更には政策に携わる人々が、これまで認識してこなかった在住外国籍大学生の知られざるデータ、存在の一旦を明らかにしたという点で、長期的に大きな意味を持つと考える。
本研究は4年後に再調査をすることで、縦断的な研究を進める予定である。将来、国籍の枠を超えてより公正な教育・職業機会を保証するために、どのような具体的行動が可能なのか、今後も建設的な議論を重ねていきたい。
筆者
早稲田大学にて博士号取得(国際コミュニケーション研究科・国際教育とコミュニケーション専攻)。現在上武大学専任講師。教育・研究の傍ら、若者のエンパワーメントにも取り組んでおり、日本での子育ての経験を活かして多様な文化的環境下での子どもの教育に関して、家族への支援活動も行っている。
備考:
- 紙面の都合上、参考文献は割愛した。また本研究では本稿で取り上げられていない他のテーマについても調査・分析を行った。本研究の詳細や他の都道府県での同様の調査の実施に関心のある方は、ご連絡いただきたい。
- 本研究は、2022年度三俣記念基金・特別研究費を受け実施した。